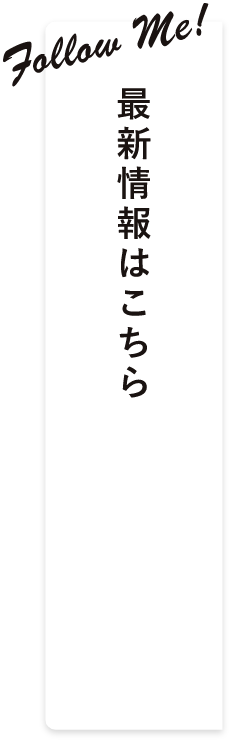今回は愛知工科大学自動車短期大学で准教授を務める加藤寛先生に、「キャリアにおける意思決定と自己理解の重要性」についてインタビューをさせていただきました。自動車工業学科に在籍されている加藤先生に、キャリアの転機における考え方や効果的な意思決定のプロセスについてお伺いします。
現在の研究されている分野・具体的なご活動内容について

インタビュアー
改めて、今回のインタビューをお受けいただき誠にありがとうございます。はじめに、現在のご研究内容や教育活動について、とくに力を入れていらっしゃる分野をお伺いできますでしょうか?
加藤先生
本学は全国で4校しかない自動車整備に特化した短期大学の一つです。
2年間で学生が「二級整備士資格」を取得することを目指しながら、整備以外の面でも学生のスキルアップを図っています。
多くの学生は、国内12メーカーの自動車販売店や輸入車販売店のサービスメカニックとなります。ですが、整備専門学校とは異なる多様な進路先、たとえば4年制大学への3年次編入や、自動車メーカー、自動車部品メーカーなどに進む学生もいます。
インタビュアー
大学での授業やゼミで教えられている内容はどのようなものがありますでしょうか?
加藤先生
私が本学に入ったころは、「キャブレター」の仕組みを教えていました。しかし、自動車の進化は凄まじく、エンジン系、シャシ系に関係なく、すべてにおいて現在の自動車は電子制御化されています。
基本的な「走る」「曲がる」「止まる」は変わりませんが、自動運転技術が進むにつれ、教育も日々進化させています。
インタビュアー
これまでの研究活動で特に印象に残っている成果や発見にはどのようなものがありますでしょうか?
加藤先生
環境問題にも興味を持ち、研究テーマとして
「学生食堂の使用済み食用油(廃食油)の有効活用」としてバイオディーゼルの研究をしています。
大学のスクールバスを、廃食油を精製した燃料で運行するという実証実験を14年にわたり行っています。学生にも、自動車を取り巻く様々な問題について授業の中で教えています。
インタビュアー
最近特に注目されている研究テーマや業界トレンドはありますでしょうか?
加藤先生
近年、自動車業界は「百年に一度の変革期」と言われています。
これらは「CASE」と言われる、コネクテッド(Connected・IoT化)、自動化(Autonomous)、シェアリング(Shared)、電動化(Electric)など、自動車の所有、利用、動力源、機能に大きな変化をもたらすということを意味します。自動車整備としては、自動車の自動化、電動化に対応した整備技術も必要となります。
研究者としてのこれまでのご経歴・キャリアパス

インタビュアー
今の仕事を志したきっかけや影響を受けた出来事・人物はありますでしょうか?
加藤先生
きっかけは、中学生の頃に
バイクのスピード感に魅せられたことです。今の若い人には死語となっていますが、当時は「三ない運動」の真っ盛りで学生の私は免許を取ることができませんでした。
しかし、鈴鹿8時間耐久レースなどを見に行く機会があり、ますますバイクに興味が沸きました。どうしてもバイクの免許が取得したくて自動車整備士の専門学校へと進学し、なんとか免許を取得することができたことから現在に至ります。
加藤先生
専門学生時代に
「普通二輪免許」「普通自動車免許」を取得し、バイクとクルマに乗りながら、整備士資格を取得しました。
就職後は、営業職と整備職を経験し、その後、知り合いからの紹介もあり、整備を教える仕事にも興味があったので、現在の短期大学に技術員として転職をいたしました。
インタビュアー
現在のキャリアを築く上で役立ったご経験はありますでしょうか?
加藤先生
技術員とは、教員の補助的な立場でしたが、働きながら通信教育で「学士」を取得。研究も行い、助手から助教へ、そして現在は准教授として教職を行っています。
インタビュアー
学生時代から現在までのキャリアパスを振り返っての気づきがあれば教えてください。
加藤先生
一貫してバイクやクルマは大好きで、学生たちとのバイクやクルマの話は尽きません。
学生時代、決して勉強は好きではなかったですが、バイクやクルマに関しては楽しく学べました。その経験から、今は学生が楽しく学べる授業を提供できるよう心がけています。バイクやクルマの技術は、日々進化し続けているため、私自身も勉強の毎日です。
現在の自動車業界に関する質問

インタビュアー
現在の自動車業界の変化・進化をどのように捉えていらっしゃいますか?
加藤先生
これからの自動車整備には、自動車の自動化、電動化に対応した整備技術も必要となります。
しかし、自動化、電動化は進んでいますが、自動車の基本は「走る」「曲がる」「止まる」であり、基本構造を理解していないと、その応用である自動化、電動化の仕組みは理解できません。何事も勉強は基本が大切です。
インタビュアー
若手人材が「ものづくりの現場」からキャリアを始める意義についてどのようにお考えですか?
加藤先生
本学に入学する多くの学生は工具を一度も触ったことがないです。また、近年は留学生も入学し、より基本をしっかり学ぶ内容となっています。
2年間という非常に短い学生生活ですが、非常に中身の濃い2年間です。
それだけに、バイクやクルマが好きな学生ばかりで、お互いに教え合いながら楽しく学んでいます。
インタビュアー
自動車業界でキャリアを築いていくにはどのような選択肢がありますか?
加藤先生
短期大学を卒業してからの進路先には、多様な選択肢があります。自動車業界には様々な職種があり、本学を卒業し「自動車メーカー」へ就職した先輩の仕事も、車両実験に携わり、実験後の車両の分解等、整備技術を生かした仕事をしているそうです。
転職者・キャリア形成中の方へのアドバイス

インタビュアー
転職を検討している方々へアドバイスをお願いします。
加藤先生
自動車整備士の仕事というと、あまり良い印象を持たないかもしれませんが、実はものすごく社会に貢献している仕事です。
日本では、国が定めた通称「車検」や「法定点検」が制度としてあり、この制度が着実に整備士によって行われることによって、狭い国土の日本において、故障車の発生は少なく、物流が滞りなく行われています。
インタビュアー
これからの時代を生きる若い世代へのメッセージはありますでしょうか?
加藤先生
留学生に話を聞くと、母国では多くの日本の中古車が走っていて、故障も少なく大変役立っていると聞いています。これも日本車は整備士によってしっかりとメンテナンスされているという証拠でもあり、海外で日本の中古車は人気となっています。
整備士の仕事は、技術があれば稼げる仕事です。自分もそうですが、好きなバイクやクルマを学び、好きなものに携わる仕事をするのは楽しい人生になると思います。
インタビュアー
今回はとてもためになるお話を聞かせていただきありがとうございました。「好きなものに携わっていると仕事も楽しくなる」ということがよくわかるインタビューでした。
愛知工科大学自動車短期大学の基本情報
今回インタビューにご協力いただいた先生は、愛知工科大学自動車短期大学で准教授を務められている加藤寛先生です。